
Nikkei Voice 2005 July
国境を越えるアート表現
デジタルアーティスト・中村元道氏インタビュー
十一月二十四日、トロントリールアジアン国際映画祭のオープニング・パーティーに、ニューヨークからビジュアルアーティストの中村元道(motomichi)氏が参加した。大勢の人で埋め尽くされたダンスフロアーのスクリーンには、体に響くダンス音楽に合わせて氏の作り出したキャラクターたちが踊った。可愛らしさと毒々しさの両方を感じさせるキャラクターたちは、一度見ると忘れられない。日本で生まれ育ち、アメリカ、南米、ヨーロッパに活動の場を広げてきた氏にとって、アート表現とはどのようなものだろうか?
●南米のストリート・サイン ニューヨークでの学生時代に出会ったパートナーがエクアドル出身だったという縁もあって、中村氏はエクアドルでデザインの会社を経営し約三年間を過ごしている。 「今のわたしの作品のスタイルはすごく南米のアートに影響されているんですよ。ストリート・サインを壁に描くんですよね。」北米では宣伝といえばポスターや看板の形で出されるのが当たり前になっているが、南米では建物の壁に描くという。選挙があれば候補者の名前や政党を壁に描く。宣伝といっても、政治宣伝もあれば商品の宣伝もあるから、ある壁には革命運動家のチェ・ゲバラが描かれて、別の壁には車の部品が描かれるということになる。
北米や日本でも、色とりどりのスプレーを使って壁に描いたグラフィティーが見られる。だがそれはごく一部の若者の流行現象であって、それぞれのサインの意味が一般の人々に理解されることは稀だ。それに比べて、南米のストリート・サインには描き手の意図がはっきりと見える。
「見た眼にはアート的な価値があると思ったんですけれど、実際それを行っている人たちにはそういう意識はなくて、単に仕事としてやっている。そのアプローチに心を打たれましたね。」
アメリカや日本ではデザインの市場が大きくなり、企業のお金でデザインのビジネスが動いてしまう。クライアントが巨大化し、デザイナーとクライアントが直接コミュニケーションを持つ機会が少なくなって、クライアントに全然会わないで仕事をすることもでてくる。 「スケールが大きくなれば、意図の分からない仕事が多くなります。ああいう路上で使う宣伝というのは、コマーシャル・アートといえば呼べば呼べますが、基礎的な面でアートに近いと思うんですよね。それが好きでよく写真とか取っていたんですけれど(笑)。」
太く力強い線とシンプルな色使いは中村氏の作品の特色だ。どこかの街角の壁に描かれていてもきっと見栄えがするだろう。また、ストリート・サインで氏を啓発した作り手と観客の近さは、氏のVJ(ビデオジョッキー)という方法で実現されているといえる。DJの流す音楽やフロアで踊る人々に呼応する形で、会場に掲げられたスクリーン上のイメージを動かすのだ。「ビジュアルミックスっていうのは、ビジュアルアーティストの表現のひとつの方法だとみているんですよ。発表の場がひとつできたような感じですね。発表するといっても、VJっていうのは観客とその場でインタラクトできるという魅力があります。観客を喜ばす、エンターテイメント性がいいですよね。」商業アートはエンターテイメント産業のモノポリーになってしまって、一方で高尚なアートは芸術の知識が豊富な人だけが分かるといった二極分化の傾向がある。中村氏がVJとして参加するイベントは、特にアートを目当てに来るという人々ばかりではない。「オーディエンスが音楽とビジュアルを楽しもうというシンプルな気持ちでいるので、こちらも楽しむ、ポジティブな雰囲気になれます。」「アートの発表の場の限界はみんな分ってると思うんですよ。アートはみんなのためにあるものだと思うので、努力をしていろんな人に開くというのは、アーティストのミッションではないかと思うんです。」
氏の作品は線の単純さなど商業アートのような親しみやすさを特徴にしている。だがその一方で、観る者の度肝を抜くような、簡単に消費させてしまわないような異物感もある。「それもリアリティの表現の方法だと思うんですよ。裏表があるといったら変に聞こえますけれど…。たとえば子供の可愛さってありますね。無邪気さですね。子供は知らないからこそ可愛いけれど、知らないからこそ攻撃的になったりとか。裏表があって人間は生きていると思うんです、シニカルなつもりではないんですけれども。愛情が攻撃性を導いたりとか。男性的なもの、女性的なものもそうですよね。一般的には分けてしまいますけれども、必ずどこかで接点はあるわけで、そこにリアリティがあると思うんですよ。」
従来は境界線が引かれてしまうものの間に接点を作り出すことが、中村氏の得意技なのかもしれない。氏がビジュアルミックスをする際に使う、VJ Moto – Japonés hasta la madreという名前の上にも、日本、南米、アメリカの歴史が重なりあっている。「ハポネス アスタラ マドレ、あえて日本語にすれば本物の日本人という意味でしょうか。メキシコ人の間で『自分は本物のメキシコ人だ』というときに『メヒカノ アスタラ マドレ』というのをよく使うんですが、実はこれはその捻りなんです。みんながいうわけではなくて、ストリートトークなんですけど。母親まではメキシコ人。自分のオリジンを言っているんですよね。」日本の外に住み始めて最初のころは、新しい場所に適応するのが精一杯。ところが長く住んでくると、逆に自分の出身をすごく意識するようになる。しかし日本に帰っても以前のようにはしっくりとは来ない。「それでもやっぱり、自分のバックグラウンドというのは否定できないんですよね。」
「メヒカノ アスタラ マドレ」はアメリカの南部や西海岸の、チカノコミュニティーで用いられている表現だという。過去にはメキシコの領土がアメリカに征服されたという歴史があり、近年は仕事を求めてメキシコからアメリカへの移民が増えている。メキシコ人だけれども、メキシコ人ではない。アメリカで生まれ育って、アメリカに住んでいる人々。ニューヨークでもスペイン語人口はかなり多いとのことである。「そういうチカノたちが『メヒカノ アスタラ マドレ』と言うのを聞いたときに、面白いなあと思ったんです。アメリカに限らずグローバルカルチャーを上手く表現するようなフレーズだなあって。『ハポネス アスタラ マドレ』って言うと、スペイン語の話せる人は必ずみんな笑うんですよね。にやっと笑うんですよ。メヒカナ…を捻って、ハポネス…にしているのが分かるんで。」
海外に長く住んで、日本人アイデンティティに強い愛着を感じるようになった人の話はしばしば耳にする。あるいはヨーロッパ中心的な文化に同化していく過程で、日本的なものから自分を切り離そうとするあまり、東洋蔑視を内面化してしまう危険もある。中村氏はどちらの両極端にも傾いていない。人や場所とのさまざまな縁からできた今の自分という個の場所から、人を楽しませつつ、アートのあり方や文化アィデンティティの通念に一石を投じている。
「『ハポネス アスタラ…』ってスペイン語で言った方が、日本語で『日本人』っていうよりも何か、ああ日本人だっていう感じがします。不思議な感覚ですよね。」
トロントでの映画祭の後は、イタリアの展覧会に参加して2004年を締めくくるとのことだった。
プロフィール
中村元道(motomichi)。デジタルアーティスト。ニューヨーク在。一九九六年パーソンズスクールオブデザインを卒業。九八年にエクアドルでデジタルアーティストとして活動開始。〇一年よりニューヨークに戻り、フリーでウェブデザイン、VJ、ミュージックアニメーションの仕事を行う。〇四年サンダンス映画祭オンライン部門入選。第80回ADC New Yorkニューメディア部門ディスティンクティブメリット賞受賞。URL: http://www.motomichi.com/
(取材・執筆:長山智香子)
2005 中村元道氏インタビュー
- Categories →
- インタビュー
- 研究
-

2014 Summer fish

-

2013 Shall We Dance?

-

2013 Un-sayable

-

1999 カエルの声

-
1998 English is my mother tongue

-

1994 あなたを

-

1997 理由なんていらない

-

1997 抱擁

-

1997 不安海岸

-

1998 鏡のなかの鏡

-
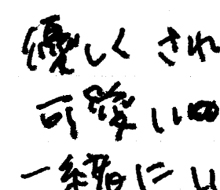
1999 まだ私は

-

1997 国際親善留学生としての豊富

-

2005 中村元道氏インタビュー

-

2005 Nikkei Voice: 「あずみ」・刺客少女のアクションコミック

-

2009 Constitutional Advocate of Peace – 日本語版

-

2008 幻影の故郷(くに)を越えて

-

2009 Constitutional Advocate of Peace – English

-

2004 “Thirst”: Water and the Human Rights Movement

-

1997 請求書

-
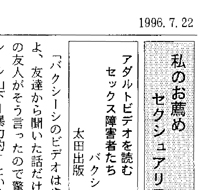
1996 アダルトビデオを読む

-
-
