
東京YWCA新聞 2008年6月号(2015年4月加筆)
幻影の故郷(くに)を越えて
社会をともに創造するために
—映画『靖国 YASUKUNI』公開によせて
長山智香子
李 纓 (リ・イン)監督のドキュメンタリー映画『靖国 YASUKUNI』が劇場公開されている。当初は四月二十一日からの公開が予定されていたものの、一般上映に先駆けて国会議員が試写会請求をし、続く政治団体の抗議をうけて映画館が続々と上映を延期する異例の事態になった。しかし公開を待望する人々の支持を受け、五月三日の渋谷シネ・アミューズを皮切りに全国各地で上映される運びとなった。
広東省生まれの李纓は、日本に住んで十九年になる。中国では中央電視台のディレクターだった。一九八八年にチベット僧侶の法会を取材していた際にデモが起こり、漢民族の李纓らは投石され、撮影を妨げられた。これを機に「民族や精神の問題、人間の心を撮らなければならない」という思いが高まるが、「そうした表現は国内においては不可能」だった。再出発を期して李纓が日本に来たその年、天安門事件が起こる。「これで本当に自分の帰る場所がなくなった」(『すばる』二〇〇一年一月号「今月のひと 李纓」)。
李纓は幼少期に、いちど住処を追われる経験をしていた。『すばる』誌のインタビューによれば、詩人だった父親が文化革命の際に下放され、彼は似た境遇にあった他の子供たちと仏教寺院で面倒を見てもらっていたそうだ。だが、幼少期に仏教者と親しんだ経験があっても、多数派民族である限り政府弾圧の前ではチベット人と同じにはなれない。そして漢民族に特権を与えるはずの中国政府が、彼に自由に表現活動できる場を与えない。
「本当に帰るべき故郷(くに)はあるのか?」―このジレンマは、実は、政治的弾圧とは無縁の人にも当てはまるのではないだろうか。室生犀星がかつて「ふるさとは遠きにありて思ふもの」と詠ったように、故郷の懐かしさや安心感は想像の中に生き生きと存在する。人が帰る場所を求めるとき、そこには世の中の変化に動じず自分を受け止めて欲しいという願いが投影されている。工業化や都市化のため社会が劇的な変化を遂げた二十世紀初頭から半ば、小説や映画などの大衆芸術は、山村に日本人の変わらぬ故郷というイメージを投影した。日本が近隣諸国を植民地化し、靖国神社に続々と英霊が「かえってきた」時代のことだ。しかし戦後の経済発展と大規模な人口移動は、過疎や廃村などの皺寄せを山村に引き受けさせた。
帰るべき故郷とは近代社会を成り立たせて来た虚構なのだと認識するとき、私たちはどんな国を想像/創造することができるだろうか。近年の芸術映画には、国や民族などの共同体意識の根っこにある共感や郷愁の仕組みを捉えようとする動きがある。『靖国』もそこに位置づけることができそうだ。
「日本人」と「中国人」の隔りを生み出すのは戦争とその記憶だ。戦争についての思いはどのように人々を繋げ、あるいは敵対させてきたのだろうか?戦時中の経験が、現在までどのように継承されてきたか。誰の苦しみに共感し、誰の痛みを軽視するよう仕向けられているか。国境のどちら側に住むかが必ずしも人を隔てるのではないと思う。敗戦から六十年余りを経て、あの戦争を直接の経験から語れる被害者が次々と亡くなっている一方で、せめて命のあるうちにと、今までタブーだった沖縄戦や日本軍の陰惨な経験を語り、「過ちを繰り返さないで」と訴える人々もいる。筆者はこの映画をまだ見ていないが、靖国神社を舞台にして、右翼や左翼の活動家、台湾や韓国の戦没者遺族、「靖国刀」を鋳造してきた刀匠らの多様な姿に肉薄するという。カメラは現実に息づく戦争の記憶を見つめ、ときには人々の相克に巻き込まれる。『靖国』上映に反対する動きは、複雑な問題だからこそ映画が紐解く道具になるという可能性を軽視しているのではないか。
2008 幻影の故郷(くに)を越えて
- Categories →
- 映画評
-

2014 Summer fish

-

2013 Shall We Dance?

-

2013 Un-sayable

-

1999 カエルの声

-
1998 English is my mother tongue

-

1994 あなたを

-

1997 理由なんていらない

-

1997 抱擁

-

1997 不安海岸

-

1998 鏡のなかの鏡

-
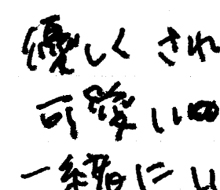
1999 まだ私は

-

1997 国際親善留学生としての豊富

-

2005 中村元道氏インタビュー

-

2005 Nikkei Voice: 「あずみ」・刺客少女のアクションコミック

-

2009 Constitutional Advocate of Peace – 日本語版

-

2008 幻影の故郷(くに)を越えて

-

2009 Constitutional Advocate of Peace – English

-

2004 “Thirst”: Water and the Human Rights Movement

-

1997 請求書

-
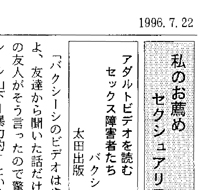
1996 アダルトビデオを読む

-
-
